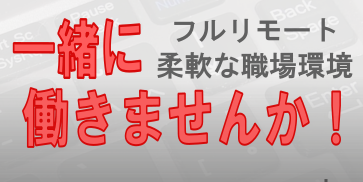クリアコードの藤本です。皆さん、Pythonでプログラムを書いていますか?
本記事から始まる前後編2回の連載では、Pythonの CFFIライブラリ — Cで実装された処理をPythonから呼び出すための仕組み — について解説したいと思います。
ここで "Cで実装された処理を呼び出す" とは、
例えば /usr/lib/libc.so に格納されているCのルーチンを、
Pythonプログラムから直接コールすることを指しています。
前編にあたる本記事では、
まず最初にCFFIライブラリの大きな仕組みについて簡単な説明を加えた上で、
実際にこのライブラリを動かしてみたいと思います。
CFFIは何を解決するのか
Pythonで会員制のWebサービスを開発しているとしましょう。
ユーザーの認証処理をセキュアに実装するために、 暗号ライブラリ libsodium のパスワードハッシュ関数を使いたいと考えたとします。 この暗号ライブラリは、もともと C(++) 向けに提供されているものなので、 何とか工夫してPythonから必要な関数を呼び出せるようにする必要があります。 どうすれば、これを実現できるでしょうか?
この問題に対する伝統的な戦略は、CPythonが提供しているC言語向けのAPIを利用して、 拡張モジュールを作成することです。具体的には次のようにヘッダ定義を読み込んで、 ラッパ関数を一つ一つ作成していくことになります:
#include <Python.h>
#include <sodium.h>
/*
* PythonのC/APIで crypto_pwhash_str_verify() 関数をラップする
*/
static PyObject* sodium_pwhash_str_verify(PyObject *self, PyObject *args)
{
char *hash, *password;
Py_ssize_t len;
int res;
// 引数をCの型に変換する (Python -> C)
if (!PyArg_ParseTuple(args, "yyn", &hash, &password, &len))
return NULL;
// 対象の関数をコールする
res = crypto_pwhash_str_verify(hash, password, len);
// 返り値をPythonのオブジェクトに変換する (C -> Python)
return PyLong_FromLong(res);
}
// 他の関数も定義してモジュールとしてエクスポートする
この戦略は20年以上に渡って用いられており、 2018年現在も多くのPythonモジュールがこの方式を採用しています。 したがって、この方式が現実に(それもかなり有効に)機能することにはほとんど異論がありません。
一方で、この方式で拡張モジュールを作成するのには、 それなりの背景知識が要求されるというのもまた事実です。 およそC/APIは実行系/ランタイムの内部実装と表裏一体なので、 CPythonに特有の仕組みや細かい決まりごと(たとえば参照カウントの扱いや例外をめぐる処理) をおさえておく必要があるからです。
CFFIはこのようなPythonとCの間の橋渡しを楽にするために開発されたFFI (Foreign Function Interface) ライブラリです。 LuaJITのFFI実装を参考に、2012年に開発がスタートしました。 2015年にメジャーバージョンの1.0.1がリリースされており、 既に2Dグラフィック処理の cairo や、 サウンドサーバーの JACK との連携などに幅広く利用されています。
CFFIはどのように問題を解決するのか
最初の例に戻りましょう。
そもそも、Cで提供される関数は(原則として)入出力が型によってきっちり定義されるので、
Pythonとの結合部分はある程度自動で生成できるんじゃないか、というのはごく自然な発想です。
例えば、int foo(const char *)という関数定義が与えられたとすると、
引数の char* をPythonのバイト列に、
返り値の int をPythonの整数オブジェクトに機械的に対応させるのは、
それほど難しいことではなさそうです。
CFFIライブラリはまさにこの"つなぎ"の部分の自動生成を行ってくれます。
実例で見てみましょう。まずは、次の内容をbuild.pyというファイルに保存します:
from cffi import FFI
ffibuilder = FFI()
# libsodiumのヘッダ情報をincludeする
ffibuilder.set_source("sodium", """
#include <sodium.h>
""", libraries=["sodium"])
# Python化したいC関数の定義を記述する
ffibuilder.cdef("""
int crypto_pwhash_str_verify(const char * hash,
const char * const passwd,
unsigned long long passwdlen);
""")
if __name__ == "__main__":
ffibuilder.compile(verbose=True)
この例では、libsodiumの関数 crypto_pwhash_str_verify() を移植しています
(上のC/APIの例で用いたのと同じ関数です)。
set_source()で読み込むライブラリを指定し、
cdef() で関数定義を与えているのが見て取れると思います。
依存関係をインストールした上で、このスクリプトを実行しましょう。 すると、CFFIが定義情報からPython向けのラッパ実装を自動的に生成し、 コンパイルまで行ってくれます:
# 必要なライブラリのインストール (Ubuntu/Debian)
$ sudo apt install python3-cffi libsodium-dev
...
# C拡張コード生成 + コンパイル
$ python3 build.py
...
# 生成結果
$ ls
build.py sodium.c sodium.cpython-35m-x86_64-linux-gnu.so sodium.o
このsodium.cがC拡張のソースコードで、
sodium.*.soというのがコンパイル済みのモジュールです。
このモジュールはそのままPythonから呼び出すことができます。 試しに、適当な入力を与えてみましょう:
>>> from sodium import lib
>>> passwd = b'secret'
>>> pwhash = (b'$argon2i$v=19$m=131072,t=6,p=1$r/g1+z50+W9RWUMRy4xu+g$'
... b'BNWoK+o6Hlcu98scoCxlNrYGo8hacShQ2nkc4RS5wZk')
>>> lib.crypto_pwhash_str_verify(pwhash, passwd, len(passwd))
0
この例で、C言語の型とPythonのオブジェクトが透過的に接続されているのが 確認いただけると思います。
残された課題/後編へのつなぎ
連載の前編を締めるにあたって、大急ぎで次の二つの点を指摘しておきたいと思います。
まず第一は、このコードジェネレーティングの戦略は万能の解決策ではないということです。 前節で見たとおり、簡単な関数であれば簡単に移植できます。 しかし、真面目にライブラリを移植しはじめると、 ほぼ間違いなく自動生成だけでは対応できないケースに出くわすことになります。
この代表例がポインタです。とくに、Cのコードでよく使われるテクニックとして 「呼び出し側でデータ領域を確保して、ポインタ経由で関数に中身を書き換えてもらう」 というコードパターンがありますが、これをどうPythonのコードに置き換えるかは、 決して自明ではありません。例えば、次の関数を移植する方法を考察してみてください:
// `size`バイト分のランダムデータで`buf`を埋める
void randombytes_buf(void * const buf, const size_t size);
この問題の解決は後編に回したいと思います。
もう一つは、CFFIライブラリの技術的な位置づけについてです。 実はここまでの「CFFI = C拡張の自動生成ライブラリ」という定式化はかなり話を端折ったものです。 この点については、他の競合する技術(Cython/ctypes/SWIG)との関係で説明する必要があるので、 後編で一節をまるまる割く予定です。